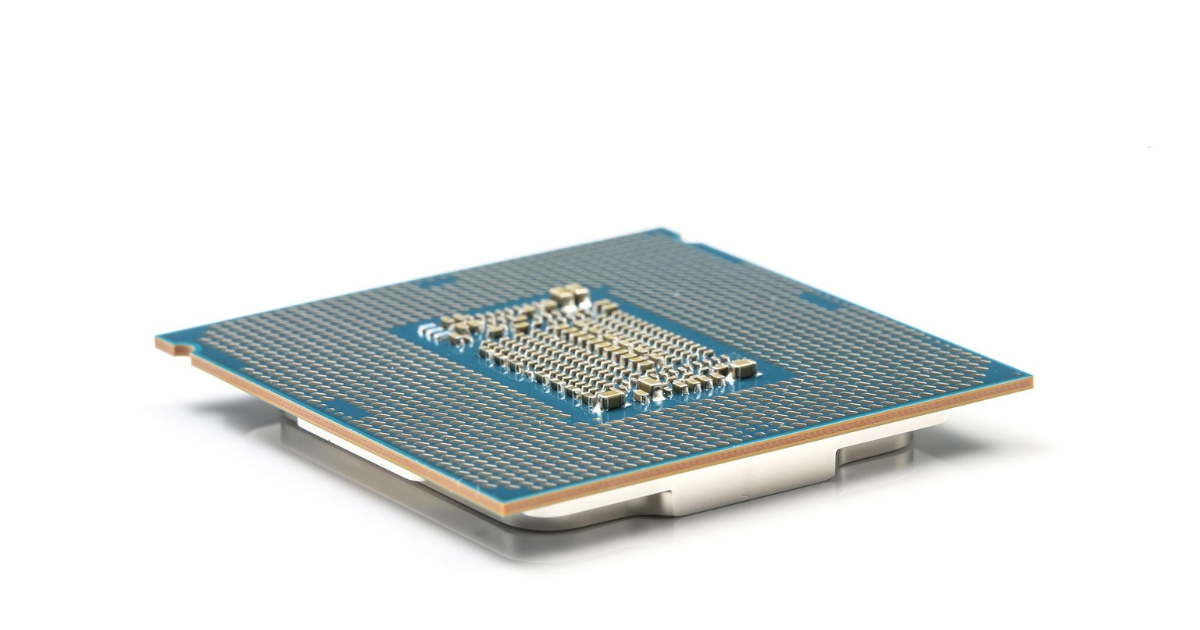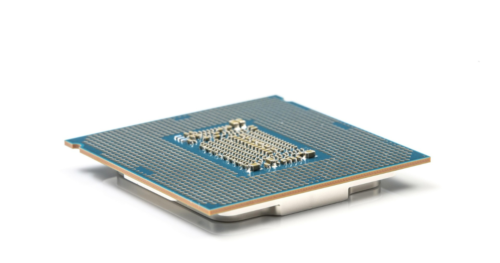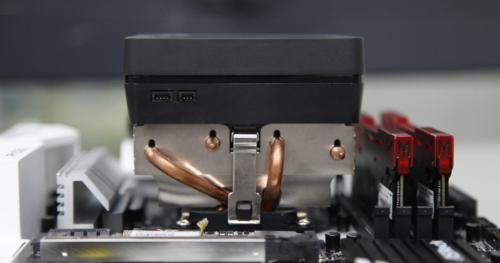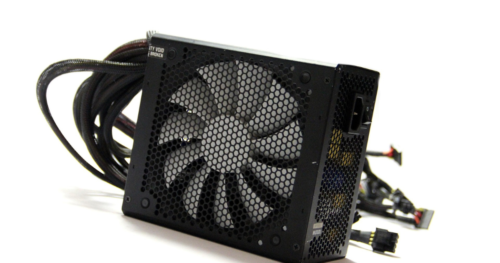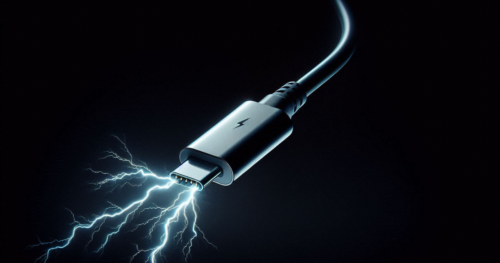今回はパソコンのカタログをベースにして、CPU品名から読み取れることやCPUの技術的な説明をしていきたいと思います。少し難しい言葉も出てきますがなるべく分かりやすく書いていきますね。
CPU名や仕様から判ること
いくつかのケースがありますがインテルのCPUを例にとります。

上の表は某パソコンメーカから販売されているノートパソコンの仕様からCPU部分を抜粋したものです。(この表は必要な情報が全て書かれておりとても丁寧ですが、CPU名称のみの記載に留まっているメーカもあります。この場合は品名でググってインテル社のWEBサイトを参照してください。)
まず、この例だとCPU名称は”インテル Core i5-1355U プロセッサー”となっていますね。
Core ix 部分
CPUの性能グレードを示します。
Core i3, i5, i7, i9 の4種類存在し、数字が大きいほどグレードが高く、後程説明するCPUコアの数やキャッシュ容量が違ってきます。i7やi9はゲームや動画編集など重い負荷が掛かる用途で選択するのが良いでしょう。稀にCore iではなく、CeleronやPentium、Intel Processorなどの名称になっている物もありますが、これらはi3よりも性能が低い廉価版のCPUになります。
13xx 部分
このCPUがインテル第13世代 Coreプロセッサーである事を示します。例えば第12世代の場合は12xxになります。xx部分はそのグレードの中の性能を示し、値が大きいほど性能(動作周波数)が高い事を示します。
U 部分
このCPUシリーズの消費電力レベルを示し、”U”の場合は最も電力が抑えられている品種を意味します。この部分は他にも”P”、”H”、”HX”などがありますが、記載順に電力が大きくなりその分だけ性能も高くなっていきます。※なおデスクトップ向けCPUではこの部分の表記の意味が全く異なります。
次に詳細部分ですが、1つづつ見ていきましょう。
10 Cores
このCPUが、合計10個のCPUコアを内蔵している事を示します。現代のCPUは1つのパッケージに複数のCPUコアが搭載されているのが普通です。CPUコアは多ければ多いほど処理性能が上がりますし、先に説明したグレードによりこのコア数が決定します。
(2 P-cores 8 E-cores)
CPUコアの内訳です。10コアのうちP-coreが2個、E-coreが8個で構成されている事を示します。このP-core、E-coreは第12世代Coreプロセッサから導入された仕組みで、P-coreは最大性能を出すためのコア、E-coreは電力効率重視型のコアで、OSの負荷のかかり具合に応じて適切にコントロールされます。例えば何も触っていない状態ではP-coreの性能を落としてE-core優先で動かすといった制御を行い消費電力を抑えます。一般的にP-Coreが多いほど性能が高いCPUとなります。
12スレッド
OSから見える実行可能なスレッド数(CPUコアの数)を示します。10コアのCPUなのに何故12コア?と疑問に思われるかもしれませんが、このCPUはP-core 1個につきOSからは論理的に2コアに見せる機能を搭載しています。元々P-coreは2コアですから、8個のE-coreと合わせて12スレッドとなります。この機能はHyperThreadingと呼ばれ、CPUがある処理を行っている最中に、処理に使われていない部分に対して時間的に同時に他の処理を投入することで処理効率を上げる仕組みです。但しこれによる性能向上は10~15%程度に留まる事が多く、あまり重要視することはありません。
更に見ていきましょう。今度は動作周波数(クロック周波数)ですね。
1.30GHz(P-cores) 0.90GHz(E-cores)
P-coreのベースクロックが1.3GHz、E-coreのベースクロックが0.9GHzという意味です。クロックは値が大きければ大きいほど高速に動きます。ベースクロックはそのCPUの基本動作周波数です。
最大4.60GHz(P-cores) 3.40GHz(E-cores)
通常はベースクロックで動作しているものの、電力的に余裕がある場合にベースクロックを上回る周波数で動作できる事を示しています。これはTurboBoost機能と呼ばれ、CPU自身が消費電力を監視しながら負荷状況に応じてクロック周波数が自動調整されます。
最後はキャッシュメモリです。
12MBスマートキャッシュ
12MBのキャッシュメモリを搭載していることを示しています。キャッシュメモリはCPUに内蔵された非常に高速なメモリで、CPUの外に配置されたメインメモリ(DRAM)との間に入っています。DRAMは容量が大きい反面、速度が遅いため、高速なCPUとの速度差が生じ処理が待たされてしまいます。これを抑止するため、メインメモリの内容をキャッシュメモリにコピーしておき、CPUはキャッシュメモリとデータのやりとりを行う事で高速化を図っています。従ってこのキャッシュメモリ容量が大きいほど事前にコピーできるデータ量も大きくなり、低速なメインメモリへのアクセス頻度が下がることから高速に処理できるようになります。
以上です。如何でしたか?
インテル第13世代Coreプロセッサーを例に、CPU仕様の見方と意味を解説しましたが、今後、インテルは第何世代という表記を止めることを表明しており、次世代のCore Ultraプロセッサーからは品名表記も少し違ったものになっています。しかしながら、品名から読み取れる情報やテクノロジーの解釈はそれほど変わりません。
パソコンの性能はCPUだけでは決まらない
CPUから見たときの仕様は、CPU性能に関わってくるものばかりでした。CPUが全体性能を決めるという考え方は正しいのですが、そのCPU処理の足をいかに引っ張らないかという点も重要です。つまり、CPU周辺の構成部品によってCPUに待たせない、忙しくさせないことが全体的なシステムパフォーマンスを上げるためには必要なのです。別の記事ではその視点で、もう少し解説を続けていく予定です。